
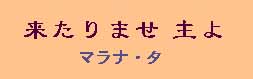

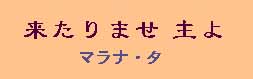
「母のいない敬老の日」
明日、5月に母を亡くして初めての敬老の日を迎えます。今まで、母と敬老の日を結びつけて考えたことはありませんでしたが、なぜか、今年の敬老の日は、母が意識されてなりません。母に対して、老人として敬う気持ちが無かったことを、今、しきりに思い知らされています。
私にとって、母は、92歳で亡くなるまで、老人というより、常に伝道の対象としての論争相手でした。浄土真宗の家に生まれた母は、日蓮宗の家に嫁いでも浄土真宗を信じていました。私が洗礼を受けるときも反対しましたし、牧師になると告げたときも猛反対をしました。私がキリスト教の話をし始めると、「私は親鸞上人を信じているから、キリスト教の話は聞かなくてもいい」と言って、私の話になかなか耳を貸してくれませんでした。
その母が、去年のクリスマスに初めて私の祈りに「アーメン」と唱和してくれました。あれほどまでに私のキリスト教の話を聞きたがらなかった母が、「アーメン」と唱和してくれたことは、私にとって、少なからぬ驚きでした。今思うと、あのときの母の「アーメン」は、信仰から来る「アーメン」というよりは、息子の優しさに応えての「アーメン」だったように思います。と言うのは、あのクリスマスの日、私は、母に伝道するというよりも、「クリスマスは神様からの全ての人への恵みの日なのだから、今日は母にこの恵みを届けよう」という思いで母の所へ出かけたのでした。そして、母に喜んでもらおうと、ケーキを用意したり、肩掛けのプレゼントを用意しました。母に「これは私と初枝(私の妻)からのクリスマスプレゼントだよ」と言って、肩掛けを肩に掛けてやると、母は「うれしい」と、子どものように肩をゆすりながら喜びを現わしたのです。
老人を敬う、それは、何より優しく接することではないでしょうか。社会的生産要員としては存在の意味がなくなったと自覚し、無意識のうちに肩身の狭い思いにとらわれている老人にとって、優しくされることは、自分の存在を肯定されたこととして受け止められるのではないでしょうか。人は、自分の存在を肯定されたと自覚するとき、生きる喜びを覚えるものです。
母がいない今、もっと老人に対する優しさで接すればよかったと、反省しきりです。私の中に優しさを生じさせてくださる老人に、感謝の思いを捧げたいと思います。