
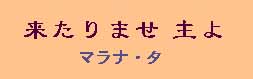

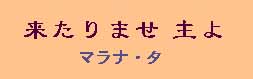
「母の入院(その1)」
92歳になって丁度1週間目の4月16日、母が肺炎で入院した。その日の夜、熊本で母の世話をしている姉から連絡が入った。母には、人工透析寸前の腎臓病がある。肺炎の治療のための抗生物質を思い切って使うか、それとも腎臓に負担をかけないためにその使用を弱めにするか、そこが、判断のしどころのようであった。これを聞いて、私には、「もしかしたら」という思いが生じた。直ぐに見舞い、というより、様子を見に飛んで行きたかったが、金曜日で、行っても直ぐに帰って来なければならないと思い、月曜日まで待った。
看護士詰め所近くの個室に入っていた母は、呼吸が速く、痰が絡んで苦しそうに見えたが、本人の気力はしっかりしていた。私を見るなり、何をしに来たのか、と言わんばかりの顔をした。私が「元気?」と聞くと、痰の絡んだ聞き取りにくい声で、「元気、元気」と応えながら、ガッツポーズをした。先に東京から見舞いに来ていた甥と姪(母にとっては孫)が帰る時間になった時など、「今度はこれを連れておいでよ」と、甥には小指を、姪には親指を立てて言う程だった。
その日(入院後3日目)、主治医から、胸部のX線写真を用いての説明がなされた。「慢性の腎臓炎があり、それが心臓肥大を引き起こしている。肺もこの通り白くなっている。今日明日、心臓が止まっても不思議ではない。延命処置はしない。問題は腎臓がどれだけもつかだが、悪化しても透析はしない。」
翌日、容態は一向に良くならず、苦しさが増すばかりのようだった。昨日の元気はなかった。私は、昨日の主治医の話を反芻していた。私は、昨日の説明を、肺炎の治療のための抗生物質は全く使わないということだと聞き違いをして、自分で決め込んでしまっていた。「腎臓をこれ以上悪化させないために抗生物質を使わないということは、このまま、肺炎で亡くなるのを待つということか。このまま、体力の消耗を待つのみなら、治療の意味はないではないか。強い抗生物質を使って、肺炎の苦しさから解放し、人間としての生き方を回復してやるべきではないか。その結果として、腎臓の機能が停止し尿が出なくなれば、その時点で、人工透析を開始すればいいではないか。」私はそう思い、知り合いの信頼する医師に電話で相談した。まず帰ってきた言葉は、「透析するかしないかは、医者が決めることではありません」ということだった。